スマホ活用術/アプリ紹介 | 2011年07月30日 | 6,900 views | Posted by harnya
harnyaです
スマートフォンっていう言葉をよく耳にするようになりましたね。
ではそもそもスマートフォンって何なんでしょう?
何だか色々機能がありそう?
難しそう?
便利そう?
高そう?
日本はケータイもかなり進化していて
ガラパゴスケータイ、いわゆるガラケーと言われるように
国内で独自のケータイ文化が発達しています。 つづきはこちら »
harnyaです
スマートフォンっていう言葉をよく耳にするようになりましたね。
ではそもそもスマートフォンって何なんでしょう?
何だか色々機能がありそう?
難しそう?
便利そう?
高そう?
日本はケータイもかなり進化していて
ガラパゴスケータイ、いわゆるガラケーと言われるように
国内で独自のケータイ文化が発達しています。 つづきはこちら »
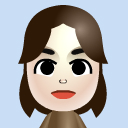
ども、harnyaです
そろそろスマホも一人一台の時代に近づいて来ているように思いますが、
ママ友によく聞かれるのが
「高くない?」
ってことです。
「節約」を常とする世の奥様方にとって月にいくらかかるのかっていうのは大きな問題
家計に負担のないくらいの金額で持てるのであれば、自分も挑戦してみたい。
という人も多いのではないでしょうか?
月7000円~10000円くらいかかってしまうのではないか?
というイメージがスマホにはあるようです。
私はNTTDoCoMoが発売されているGALAXY Tabを使用しているのですが
(厳密にはスマホというよりタブレット端末になるようですが)
GALAXY tabにかけているのは月2500円程度です。
今日、子どもをパパに押し付けて(^-^;友人と観にいってきました
この映画、主演のジェット・リーがノーギャラでもいいからと出演を切望した作品です。
友人に教えてもらって観た予告編で既に号泣・・・
 7月17日に早稲田大学でおこなわれた国内最大規模のAndroid関連イベント「Android Bazaar and Conference 2011 Summer(ABC 2011 Summer)」に参加してきました。
7月17日に早稲田大学でおこなわれた国内最大規模のAndroid関連イベント「Android Bazaar and Conference 2011 Summer(ABC 2011 Summer)」に参加してきました。
主な目的は「日本Androidの会 福祉部」のカンファレンス発表を聴講するためです。
「日本Androidの会 福祉部」とは、その名のとおり障害を持つ方やご高齢の方など、何らかのサポートを必要としてい方たちの為にAndroid端末を積極的に活用していこう!という有志の人たちの集まりです。
先日、NHKで放送された「福祉ネットワーク ~ ぼくの気持ちを伝えたい」で福祉部の活動が取り上げられていましたが、そのときから大きな関心をもっていましたので、今回のイベントはまさにタイムリーでした。
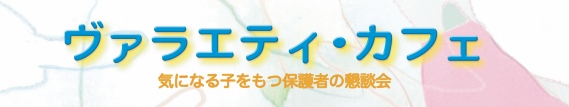
発達が気になる子どもをもつ保護者が、発達障害の専門家や先輩保護者、成人当事者と自由に懇談できる場「ヴァラエティ・カフェ」がスタートします!
「ヴァラエティ・カフェ」は、レデックス(こども脳機能バランサーの開発元)の五藤博義さん、大田区自閉症の子をもつ親の会コーディネーターの原佐知子さん、東京都成人発達障害当事者会イイトコサガシの冠地情さんなどが発起人となりスタートした会で、私も実行委員の一人としてお手伝いさせていただいております。
いよいよ7月30日(土)に第1回目の集まりが、下記のとおり開催されます。当日は、私も子どもといっしょに参加する予定です。一人でも多くの保護者や関係者の方とお話できたらと思っておりますので、ご興味のある方は是非ご参加ください。
お申込み方法等は下記の要項をご覧ください。
7月7日~9日に東京ビッグサイトで開催された教育ITソリューションEXPOに参加してきました。
近年、「ICT教育」「教育のIT化」「デジタル教科書(電子教科書)」といったキーワードが広がりをみせる中、学校向けのIT展示会として昨年より始まったのが「教育ITソリューションEXPO 」(EDIX/エディックス)です。
第2回目となる今年は出展企業550社、学校・教育関係者1万5,000名が来場する国内最大級の教育IT専門展になったとのこと。
iPadやAndroid端末を活用した授業事例など興味深いセミナーもいくつかあったのですが、今回は下見ということで展示ブースを中心にいろいろ観て回りました。
未来の学校をイメージ? 東芝情報機器ブース

こちらの写真は東芝情報機器のブース。未来の教室をイメージしたセミナー用ブースが目を引きました。本当にこんな教室があったら楽しく授業を受けられそうですね。
本日より、Keaton.com Blog がスタートしました!

当ブログでは、「親子で楽しむスマートフォン!」と題しまして、家庭内でのスマートフォン活用術や、パパ、ママ、そしてお子さんが便利に使えるアプリなどを紹介していく予定です。
また、障害者のためのサポートデバイスとして、スマートフォンなどの携帯端末を活用していこうとする動きが日本でも広がっていますが、いわゆる「福祉アプリ」についても積極的に取り上げていけたらと考えています。